スケッチサイズとスケッチ材とは
アルミニュウム限らず鉄の鋼板などは、コイル材、スケッチ材、定尺材などでユーザーであるメーカーの工場などにお納めしています。スケッチ材は、必ずしも小口で少ないとは限りません。
納入先の工場では、それぞれ加工する部品の種類や工場にある設備や機械の種類によって、コイル材、スケッチ材、定尺材を選ぶことになります。
大量にお使いなるのであれば、コイル材で圧延したものを切断せずに納めることが多くなります。少量の小ロットであれば、スケッチ材、定尺材のほうが多くなります。定尺と違ってスケッチ材は寸法を指定して購入することができるのが利点です。
スケッチ材は「切り板」(きりいた)と呼ばれることも多くあります。工場などの現場では、この「切板」の呼び名が一般的かもしれません。
また「四方」(しほう切ぎり)と呼ばれることもあります。「四方」(しほう切ぎり)は、耳付きの板に対して、耳を切り落とされて出荷されている状態の板を指しています。別名がこの「スケッチ材」になります。スケッチ材は、英語ではSketch blank(スケッチブランク)と表記されます。
いずれにしても「スケッチ材」とは、コイルの状態で、巻かれている製品ではなくて、切断面が綺麗にされた、いわゆる「平板」の状態のアルミニウム製の板ということになります。
大量生産でメインに使われる場合は、コイル材で納入されて使われることが多くなります。コイル材であれば、プレス機などにセットすると、そのまま材料が供給されていくために、生産効率がよい方法となっています。
プレス加工などでは、なるべく捨てる材料が少なくすむようなサイズのアルミや鋼板を用いることで原価を下げることができますので、コイル材を使うケースが多いようです。
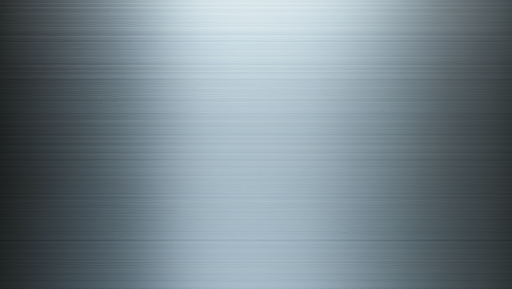
スケッチサイズの具体例
スケッチサイズのシートは、無駄のないサイズにして、歩留り向上を図ることができます。
お客さんの必要サイズや必要数量に対応して納品します。
一般的には、圧延メーカーでは、基本的には、圧延したあとの状態のコイルで出荷しますが、そのあとで、コイルセンターなどに持ち込まれて、このスケッチサイズに切断されてお客さんのところに納品されます。
- スケッチサイズのメリットとしては次のことがらがあります
- 指定の寸法であれば、定尺から切断するよりも歩留りが上がります
- 手作業ではなく、機械作業でカットするためので対角・切断公差・表面などの品質が向上します
ただし、切断機によって、寸法がある程度決まってきます。
- たとえば、このような仕様になります。
- スリッターの場合、5052S相当で板厚0.3~2.0mm、幅13~1,310mm
- レベラーの場合、5052S相当で板厚0.3~3.0 mm、幅100~600 mm、長さ170~2,000 mm
- 公差は、幅+0 mm、-0.3 mm、長さ±0.5 mm

(ご参考)「定尺」
鋼材の定尺は、法令企画(JIS)や協会規格、メーカーなど企画寸法のことです。管とか棒にもありますが、板の場合は、サブロクやシハチなどのいろいろな定尺というのがあります。
定尺は、歩留りなどがよくなるようにして板取りもよくなるように工夫して設計することで材料のコストをさげることができるようになります。
アルミの場合であれば、流通量の多いA5052のアルミ板などの特定の規格のもとつくられたメインの商品となる板材ということになります。
具体的な「定尺」の寸法
アルミニウムでよく利用されるサイズは4種類ありますが、材料のサイズはJIS規格です。
サブロク、ゴトーのミリの換算ですが、1フィート=304.8㎜を基準になっています。
(サブロク)3X304.8㎜=914.4㎜ 6X304.8㎜=1,828.8㎜
(ゴトー)5X1.524㎜= 10X304.8㎜=3,048㎜
メーター板(メーターバン)はそのままの名前になっています。
・3×6 通称サブロク
914㎜ × 1,829㎜
・4×8通称シハチ
1,219㎜ × 2,438㎜
・5×10 通称ゴトー
1,524㎜ × 3,048㎜
・メーター板(メーターバン)
1,000㎜ × 2,000㎜



コメント